
将来に備えて、地元の司法書士の先生に任意後見人になってもらおうと思っているんだけど、費用っていくら位かかるのかな?

任意後見契約の費用は、司法書士や行政書士などの専門家によって、バラバラです。また、本人の財産額によっても異なります。
ただ、月額の費用だけでなく申立てに関する費用など、契約初期の費用も発生します。
今回は、任意後見契約を専門家に依頼した場合にかかる費用について解説します。
任意後見契約の費用

大きく分けて3段階に分かれます。
最初に任意後見人と契約内容を定めるときの①契約書の作成段階。
次に、本人の認知機能が衰えて、②裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる段階。
ここで、最初に締結した任意後見契約の効力が発効することになります。
さらに、契約発効後、③任意後見人と任意後見監督人に支払う月額報酬が発生します。
契約書の作成段階
任意後見契約の契約書は、公正証書で作成する必要があります。
そのため、戸籍や住民票の取得、本人確認のための印鑑証明書の取得の費用が掛かります。
それに加えて、専門家に依頼する場合は、報酬が別途発生します。
- 公証役場の手数料 1万1000円
- 印紙代 2,600円
- 登記嘱託料 1,400円
- 書留郵便料 約540円
- その他雑費
- 専門家に支払う報酬 10万~30万円前後
任意後見監督人を選任する段階
契約後、本人の判断能力が衰えた場合、任意後見監督人の選任の申立てが必要になります。
その申立ての準備として、本人の判断能力の衰えを証明するために医師の診断書が必要となります。
この作成費用が、医療機関にもよりますが、数千円発生します。
また、任意後見監督人選任の申立書の作成を専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
- 申立て費用 800円
- 登記費用 1400円
- 予納郵券 3700円
- 専門家に支払う報酬 10万円~15万円前
契約発効後の月額費用
任意後見人に支払う報酬
無事に任意後見監督人が選任され、任意後見人としての業務が発生すると、任意後見人に支払う月々の報酬が発生することになります。
親族が後見人に就任する場合、契約によって報酬を無報酬とすることもできます。
第三者が後見人に就任する場合は、本人の財産額に応じて決められることが多いです。
だいたい月に3万円から5万円くらいが相場といえます。
任意後見監督人に支払う報酬
さらに、任意後見監督人に支払う月々の報酬も発生します。

任意後見監督人には、必ず報酬を支払わないといけません。
これは、家庭裁判所の審判により決められるので、いくらになるのかは契約時にはわかりません。
大体、月額1~2万円くらいが相場です。
注意点

えっ!任意後見契約をすると、毎月費用が掛かるの!?
それはちょっと困るかも・・・負担もけっこう大きいしね。
ここで、気を付けるポイントを1つ。
任意後見契約を締結したからといって、すぐに月額費用が発生するわけではありません。
費用が発生するのは、あくまで本人の判断能力が衰えて、後見監督人選任の申立てがなされた後からです。
本人の判断能力が衰えることなく、そのまま亡くなった場合は、後見監督人選任の申立てはなされないわけですから、任意後見の効力は発効しないまま終了、というわけです。

よく任意後見は、「頭の保険」だとか、「もしもの時の備え」と言われることがあります。
これは、「海外旅行保険」や「地震保険」、「火災保険」などの保険商品のように、まさかの時に備えて事前にお金を掛けておき、いざ問題が発生したときに保険金でカバーされるのと同じ仕組みなのです。
任意後見も、意識がしっかりした段階で契約を結び、万が一認知症になったら、任意後見人が報酬を受け取る代わりに、本人の面倒をみてくれる、というものです。
結局のところ、本人に何の問題もなければ、他の保険商品と同じように、任意後見人が付くこともなく、当然費用も発生しないのです。
毎月の費用が発生するのは、あくまで「本人の判断能力に問題があった後」の話です。

なんだ~、そうなんだ!
これから認知症にならないよう、今からしっかり脳トレや運動をしっかりしておかないと!これも「未来への投資」ってやつだな!
わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
「調べてもよくわからない、、、」
終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。
そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
千葉市で相続・終活窓口を運営している行政書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。
LINEの「友達になる」ボタン又は、お問い合わせボタンから必要事項をご入力の上、ご連絡ください。
LINEで今すぐ相談
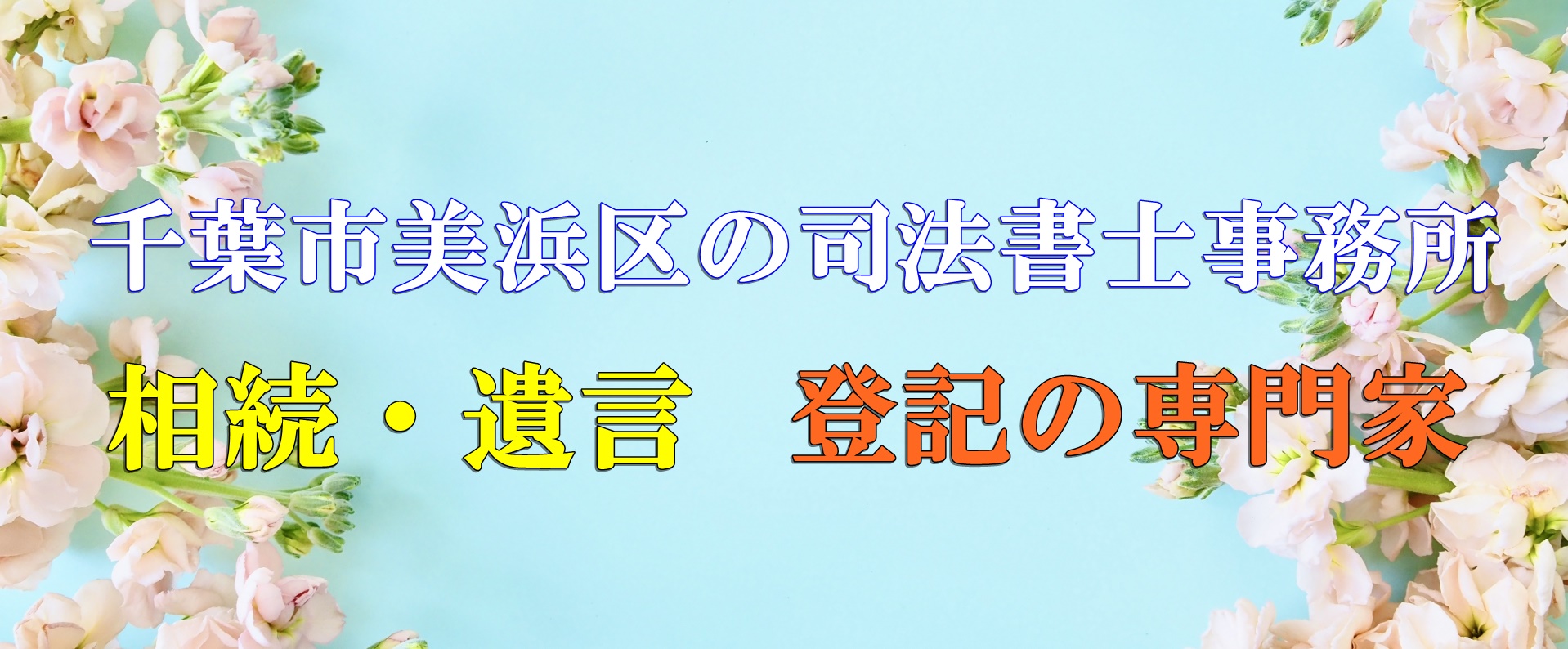
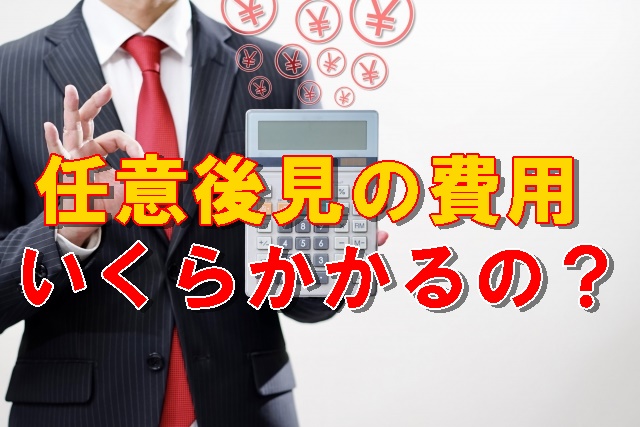
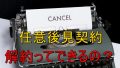
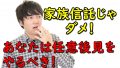
コメント